 |
金沢城は,加賀一向一揆の本拠地,金沢御堂としての時代や佐久間盛政の時代を経て,天正11年(1583年)の前田利家入城後は,加賀藩主前田家の居城として本格的に建造が行われた. 天守閣は慶長7年(1602年)の落雷による焼失後は再建されなかったが,櫓の数は多いときでは20棟を数えたといわれ,鉛瓦や海鼠塀が貼られた石川門や,三十間長屋など,金沢城独自の偉容を誇ったと伝えられている. 明治期には兵部省,昭和期には金沢大学が置かれ,現在は金沢城公園として整備されている. |
 |
|
 |
|
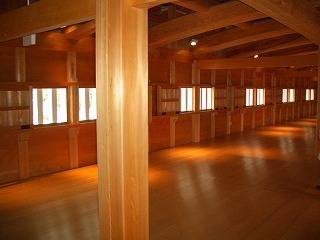 |
|
 |
|
 |
|
 |
金沢城では,前田利家の入城後,本格的な石垣づくりがはじまりました.出入口や庭園といった場所に応じて,特殊な技術やデザインが工夫されたこと,また,何度も修築が繰り返されてことから,現在,さまざまな種類の石垣を見ることができます. さらに,石垣づくりの秘伝書,石を切り出した丁場,石引き道の存在など,石垣に関する歴史資料や環境が備わっていることをあわせ,金沢城は「石垣の博物館」とおばれています. 写真は野面積みという積み方で,3つの積み方の中で元も古いもので,自然の石や粗割りしただけの石を用いて積む技術です.金沢城の初期の姿を伝える数少ない貴重なもので,城内では,東ノ丸北面石垣などに見られます. |
 |
打ち込みハギ 形や大きさをそろえた割石を用いて積む方法で,櫓や長屋などの外周の石垣に見ることができます.二ノ丸北面石垣は,加賀藩石垣技術者,後藤彦三郎が「城内屈指の石垣」と絶賛しています. |
 |
切り込みハギ 割石を丁寧に加工し,隙間なく積み技法で,本丸への入り口など城の重要な部分の石垣にみることができます. |
 |
|
 |
|
 |
唐崎松 13代藩主前田斉泰が,琵琶湖の松の名所唐崎から種子を取りよせ育てた. |
 |
眺望台 ここからの眺めは兼六園の六勝のうちの1つ「眺望」を味わうことができる. |
 |
初代姫小松 推定樹齢500年を数えていたが初代姫小松.その枝ぶりのよさは園内一を誇っていたが,度々の台風による被害と老衰により,主幹の一部を残し平成17年の6月に伐採された.左は2世である. |
 |
雁行橋 |
 |
日本武尊の像 明治10年(1877年)西南の役で戦死した郷土出身の将兵を祀った記念碑である.銅像の身長5.5m,台座の高さ6.5mで明治13年(1880年)に建てられた. |
 |
|
 |
根上松 13代藩主前田斉泰(1822〜1866)が,稚松を高い盛土にお手植えし,徐々に土を除いて根を表したものと伝えられる. |
 |
|
 |
|
 |
芭蕉の句碑 「あかあかと日は難面も秋の風」 元禄2年(1689)芭蕉が金沢で作った句 |
 |
御室の塔 この五重の塔は,京都の御室御所(仁和寺)の塔を模したものといわれ,この名がある. |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
霞ケ池 天保8年(1837)に掘りひろげられた池で,広さは5800平方メートル 池の中の島は,蓬莱島といい,不老長寿を表しており,また亀の甲の形をしているので,別名,亀甲島ともいう. |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
竹根石手水鉢 この手水鉢は竹の化石のようにみえるため,この名があるが,椰子類の茎と根の化石で,学術上極めてめずらしい. |
 |
伯牙断琴の手水鉢 表面には中国の琴の名手「伯牙」が友人の死を悲しんで琴の弦を断ったという故事が浮き彫りにされている.金工「後藤程乗」の作といわれる. |
 |
夕顔亭 安永3年(1774)に建てられた茶室.袖壁に夕顔(瓢箪の古語)の透かし彫りがあるので,夕顔亭という.本席は三畳台目で相伴畳を構えた大名茶室.藩政時代は「滝見の御亭」とも呼ばれていた |
 |
瓢池 昔このあたりを蓮池庭といい兼六園発祥の地である.池は瓢箪形をしているので後に瓢池と名付けられた. 前方の翠滝は安永3年(1774)につくられたものである. |